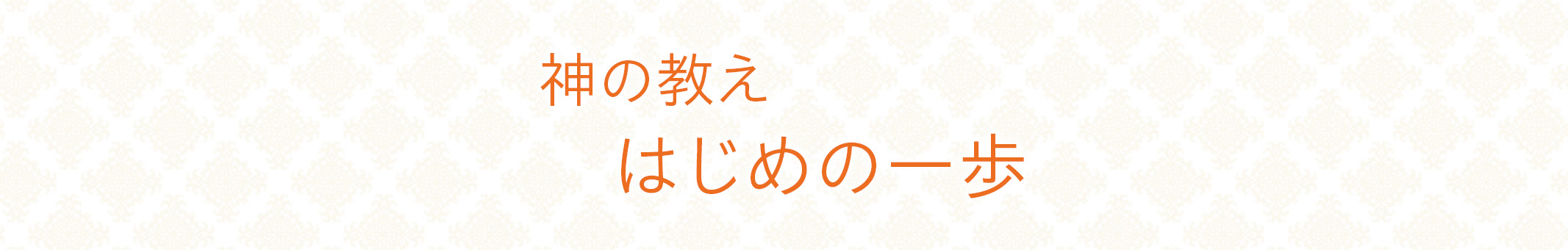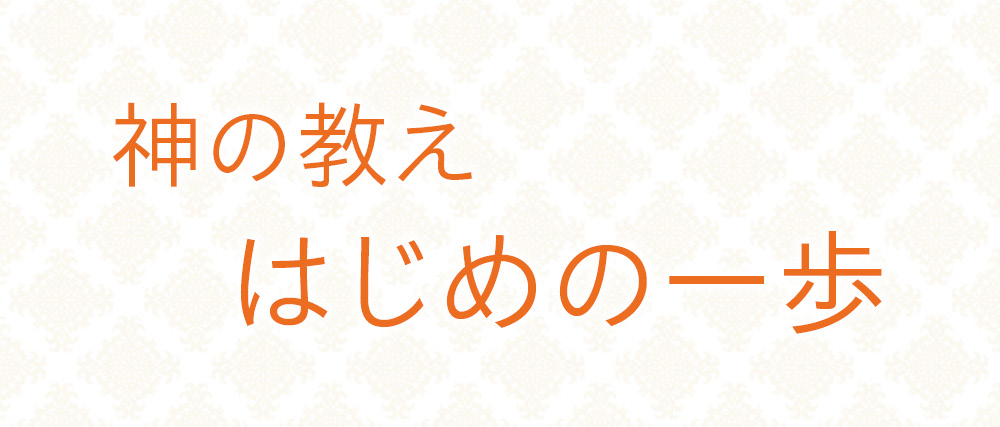本物の“しあわせ”とは?
人間と神様、その関わりは、何から始まったのでしょうか――。
しあわせを求めて、神に願いを
昔々、天気予報もない時代。「そろそろ雨が降るように」「早く嵐に去ってほしい」。五穀豊穣(ほうじょう)を願って求めた、神の力。
その存在を信じる人、信じない人、どちらもいるのが事実です。それでも、学問の神様、縁結びの神様、金運アップの神様…と、今なお人間は、いろいろな場面で神に手を合わせ、お願いをしています。
それはなぜかと言えば、誰もが「しあわせになりたい」から。いい大学に入りたい。いいパートナーに巡り合いたい。お金に不自由したくない。自分の願望がかなったとき、多くの人が「しあわせ」を感じるでしょう。
しあわせって、はかないもの?
しかし、せっかく「しあわせ」と思っても、もっと優秀な人に出会った途端、「負けた…」としょんぼり。パートナーの欠点が見えて、「こんな人とは思わなかった」。喜びが、あっという間に消えてしまうこともあるのが現実です。
さらには、その喜びが、不幸を運んでくることまであるのです。「お金はたまったけれど、相続でもめ事が…」「念願のマイカーを購入したのに、事故に遭って…」。願いがかなって満たされた心が、一気に悩み、苦しみへと暗転。人間がイメージする「しあわせ」は、実にはかないものです。
神が“仕合せ”と表される理由
それでは、「永続するしあわせ」とは、何なのでしょうか。ご一緒に考えてみましょう。
大山命は、“しあわせ”を、「幸せ」でなく、「仕合せ」と表されます。人間は、一人では生きられず、誰もが必ず支えを頂いて生きています。半面、自分も、人の役に立てる力を持っています。その力を、お互いが相手のために「仕え合う」ところに得られるもの。それが、全ての人が味わえる、本物の“しあわせ”なのです。
相手を思って関わると言っても、特別なことをするわけではありません。話に親身に耳を傾けたり、落ち込んでいる人に、「大丈夫?」とひと声掛けたり。ささやかでも、いつも人の心を大切に、相手の気持ちが明るくなるように関わる…ということです。そのような人を、周りも放っておかないでしょう。集まりがあれば、「ぜひ一緒に」と誘われたり、何かと意見を尋ねられたり。みんなに慕われ、必要としてもらえます。その時に味わうのが「生きがい」。神が、全ての人に手にしてほしいと願われる「仕合せ」です。この「仕合せ」は、人生の終日まで得られます。かつて、直使供丸姫先生は、このようにお話しくださいました。
「老人を大切にして何もさせないより、『自分はこの家で大切な仕事を受け持っている』という意識を持ってもらうことが、生きがいになるのです。『何もしなくていいから…』『年を取っているから…』そのように言われるよりも、『いてもらわないと困る』と言われれば、『もっと長生きをしなければいけない』と、生きる意欲が出ます。それが、生きがいであり、仕合せにつながります。
人間の生きる喜び、仕合せとは、人の役に立つ意識から起こるのです」
人を思いやり、支え、相手からも補ってもらう。人と仕え合って得られる「仕合せ」は、いつまでも消えない、心の宝物です。温かく人と関わることで、周りの人たちと調和しながら縁を深めていけます。出会いを生かした分だけ、「生きがい」を味わうことができ、人生が豊かに実っていくのです。
神 示
人間が真に求める仕合せ 幸福は
形ではない
多くの人との出会いに感謝し 感動し
共に味わう調和心にある
(平成28年4月29日)
※神示とは、大山命が使者を通して表されるお言葉。詳しくはこちら